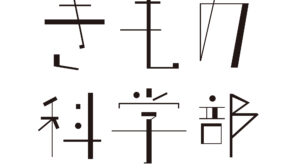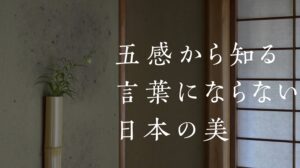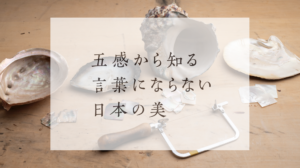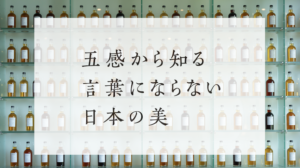教育普及
千總文化研究所は、次世代育成支援を目的として、日本の文化芸術を大人が学ぶ体験型プログラムを、2024年11月からスタートしました。第一線で活躍する表現者・技術者をお招きし、五感をテーマとしたご講演と感性や感覚に立ち返って文化芸術を深く知る体験をご提供するプログラムです。本プログラムの収益は、当研究所が企画・開発を進める次世代育成プログラムの運営に充てられます。 第5回は、能楽小鼓方大倉流16世宗家・大倉 源次郎先生(重要無形文化財保持者)をお招きして、1904年創建の京都で最も長い歴史を持つ大江能楽堂にて開催いたしました。本回は、大倉先生のご講演とともに囃子の演奏に加え、シテ方金剛流…
千總文化研究所は、次世代の創造性育成を目指して2021年より染織技術や染織文化を題材とした教育プログラムの企画開発を、教育工学の専門家の協力のもとに進めて参りました。この度、2024年10月から2025年2月にかけて開催された、中学生・高校生のための課外プログラム「きもの科学部」の成果発表展示を下記のとおり開催いたします。 期間:2025年9月15日(月)~10月24日(金)水曜休館 10:00~17:00(開館時間は、千總本店の営業時間に準じます。)場所:千總本店2階(京都市中京区御倉町80)入場料:無料主催者:一般社団法人千總文化研究所 「きもの科学部」は、日本の伝統…
千總文化研究所は、三笠宮家の彬子女王殿下が講義される京都産業大学文化学部京都文化学科の開講科目『京都文化特殊演習』の授業に協力させていただいています。本科目は、彬子女王殿下ご自身が総裁を務められている心游舎(しんゆうしゃ)との共催により、毎年異なるテーマが設定され、日本文化を学ぶ子供達のためのプログラムを大学生が企画するものです。2025年のテーマは、「きもの」。5月から授業が始まり、10回にわたる演習時間の中でディスカッションを重ね、プログラムのテーマとワークショップの内容を検討してきました。 授業の一環として千總本店、ギャラリー、手描き友禅の工房見学を行い、子供達に着物のどのよう…
千總文化研究所は、次世代育成支援を目的として、日本の文化芸術を大人が学ぶ体験型プログラムを、2024年11月からスタートしました。第一線で活躍する表現者・技術者をお招きし、五感をテーマとしたご講演と感性や感覚に立ち返って文化芸術を深く知る体験をご提供するプログラムです。本プログラムの収益は、当研究所が企画・開発を進める次世代育成プログラムの運営に充てられます。 第4回は、千家十職・竹細工柄杓師14代の黒田正玄先生をお招きして、京都の老舗旅館・柊家にて開催いたしました。本回は、黒田先生のご講演、黒田先生の作品を用いたお茶席体験と、柊家館内ツアーにて約2時間のプログラムとして構成されまし…
千總文化研究所は、次世代育成支援を目的として、日本の文化芸術を大人が学ぶ体験型プログラムを、2024年11月からスタートしました。第一線で活躍する表現者・技術者をお招きし、五感をテーマとしたご講演と感性や感覚に立ち返って文化芸術を深く知る体験をご提供するプログラムです。本プログラムの収益は、当研究所が企画・開発を進める次世代育成プログラムの運営に充てられます。 第3回は、 漆芸家の小西寧子様にご登壇いただき、依水園・寧楽美術館(奈良市)にて開催いたしました。本回は、小西様のご講演、小西様の作品を用いたお茶席体験、庭園見学にて約2時間のプログラムとして実施され、16名の方が…
千總文化研究所は、次世代育成支援を目的として、日本の文化芸術を大人が学ぶ体験型プログラムを、2024年11月からスタートしました。第一線で活躍する表現者・技術者をお招きし、五感をテーマとしたご講演と感性や感覚に立ち返って文化芸術を深く知る体験をご提供するプログラムです。本プログラムの収益は、当研究所が企画・開発を進める次世代育成プログラムの運営に充てられます。 第2回は、サントリー株式会社チーフブレンダーの福與伸二様にご登壇いただき、サントリー山崎蒸溜所にて開催いたしました。本回は、福與様のご解説による山崎蒸溜所見学とご講演、ウイスキーのテイスティングとブレンディング体験…
2024年「きもの科学部」第6回を開催しました。今回のテーマは「デザイナーって何をつくる人?」講師は、株式会社千總で染織品のデザイナー・ディレクターをされている今井淳裕さんをお招きしました。前半の講義では、まず着物を作るときのステップを解説いただきました。着物のコンセプトやテーマを考えること、アイディアをイメージすることやどのような技術を用いてイメージを形にするか、そして着物を作るには様々な工程がありそれらが分業で成り立っていて、チームワークが大切であることなどをお話しいただきました。 さらに、「描画力」「構成力」「知識」「発想力」といったデザイナーに必要なスキルに触れた上で、実際に…
2024年「きもの科学部」第5回を開催しました。今回のテーマは「着物に描かれているものは?ー文学編ー」講師は、日本古典文学がご専門で大阪工業大学准教授の横山恵理先生をお招きしました。着物には古来さまざまな模様が描かれてきましたが、文学にまつわるものも少なくありません。風景の中に物語の一場面を再現したものや、漢詩や和歌などをそのまま文字で表したのもの、あるいはそうした文芸を暗示する動植物を表したものなどがあります。 今回は、日本古典文学の『枕草子』を軸に日本の自然観を学び、美しい自然からインスピレーションを得た和歌の世界を探求しました。前半のワークショップでは、江戸時代の小袖の観察をし…
2024年「きもの科学部」第4回を開催しました。今回のテーマは「着物に描かれているものは?ー植物編ー」です。講師は、植物学者で滋賀大学名誉教授の木島温夫先生をお招きしました。 着物には古くから、写実的にあるいは抽象的に様々な植物が描かれてきました。その多くに、植物の生態や姿形の特徴になぞらえて長寿や子孫繁栄などおめでたい意味が込められています。では、その植物たちはいつどこから日本にやってきて、どのような特徴を持っていて、人はどのように植物と共に生きてきたのか、知っているようで知らない植物の世界を人文科学と自然科学の視点から探究しました。前半は、植物がもたらした文化に着目し…
2024年「きもの科学部」第3回を開催しました。今回は、当研究所が教育プログラム開発の共同研究を進めている金沢大学から、吉武希実さん(金沢大学融合学域先導学類2年)が参加し、レビュー記事を作成してくれました。 ーーーーーー今回のワークショップのテーマは「五感を使って植物を観察しよう」でした。中学1年生から高校3年生までの7名が参加し、京都府立植物園を舞台に、五感を駆使して植物観察を行い、自然の魅力を体感しました。 前半は植物園ガイドの立花さんに15,000平方メートルもの広大な園内の一部を案内していただきました。植物の特徴や生活への応用…